灯籠の購入を考えたとき、まず気になるのが「値段の相場はいくらくらいなのか」という点ではないでしょうか。設置場所や目的によって選び方が異なるため、どの灯籠を選べばよいか迷う方も多いはずです。
この記事では、灯籠の種類ごとの特徴や設置方法に加えて、灯籠の値段相場についてもわかりやすく解説します。庭や墓への設置に適したタイプ、高級石材と安価な灯籠の違い、購入先の選び方やインテリアとしての活用例など、幅広い情報を網羅しています。
初めて灯籠を選ぶ方でも安心して検討できるよう、実用的なポイントをまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください。
- 灯籠の価格帯と高級品・安価品の違い
- 種類ごとの灯籠の特徴と用途
- 設置場所に適した選び方とポイント
- 購入先や設置時にかかる追加費用
灯籠の種類と価格・値段の相場を知る
灯籠の値段の相場はいくらほどなの?

灯籠の価格は、素材やデザイン、サイズによって大きく変動します。一般的な価格帯は、3万円から10万円程度が多く見られる相場です。
価格に幅があるのは、使用する石の産地や加工方法、装飾の細かさなどが大きく影響するためです。安価なものは主に中国などの海外産石材が使われており、デザインもシンプルなものが中心です。逆に、国産の高級石材や手彫りによる装飾が施されたものは、30万円を超えることも珍しくありません。
例えば、庭園や墓前に使われるスタンダードな置灯籠であれば、手ごろな価格のもので3~5万円台から購入可能です。一方で、伝統工芸品として認定された岡崎産の石灯籠や、細部にこだわった美術品クラスの灯籠は、100万円を超えるケースもあります。
ただ、価格が高いものほど必ずしも自宅や墓所に合うとは限りません。設置場所の広さや周囲とのバランス、メンテナンスのしやすさなども踏まえたうえで選ぶことが大切です。
なお、購入費用とは別に、設置にかかる運搬・施工費が2万円~5万円ほど必要になることもあります。あらかじめ見積もりを取って、総費用を把握しておくと安心です。
灯篭のお値段は3万円~10万円程度が相場といわれていますが、質の良い高級な石を使って作られたものやデザインが緻密で繊細なもの300万円以上する場合もあります。
引用:墓石コネクト
一般的なお墓に設置する場合に人気なのは、中国産の3~5万円程度の灯篭でデザインも無難なものが多いのでオススメです。
石灯籠の種類とそれぞれの特徴

石灯籠にはいくつかの種類があり、それぞれ設置目的や見た目の特徴が異なります。どの種類を選ぶかは、設置場所や演出したい雰囲気によって決めるのが一般的です。
まず代表的なのが「春日灯籠」です。これは神社仏閣に多く見られる背の高い灯籠で、六角形の笠と円柱の柱が特徴です。格式ある印象を与えるため、荘厳な庭や墓所に適しています。
次に「雪見灯籠」があります。これは背が低く、3本または4本の足で支えられているタイプで、大きな丸い笠が特長です。名前の通り、雪景色との相性がよく、池の近くや庭園に向いています。
「置灯籠」は、小型で柱を持たず、直接台や地面に置かれるシンプルなタイプです。限られたスペースにも設置しやすく、家庭の玄関先や小さな庭でも使いやすい灯籠です。
さらに「活込灯籠」というタイプもあり、これは柱を地面に埋め込んで設置する様式です。コンパクトでありながら風情を演出でき、茶庭や坪庭などによく用いられます。
これらの石灯籠は、使用される部材にも違いがあります。たとえば、春日灯籠は宝珠・笠・火袋・受け・柱・地輪の6部構成、雪見灯籠は足が特徴的で、地面に安定感を持たせる設計になっています。
それぞれに趣があり、和風空間の演出に大きく貢献する石灯籠ですが、選ぶ際にはデザインだけでなく、設置の安定性や目的に合ったサイズ感も確認しておくと失敗が少なくなります。
人気の庭園用灯籠と選び方


庭園用として人気のある灯籠には、雪見灯籠・春日灯籠・置灯籠などがあります。これらは見た目の美しさだけでなく、設置する目的や場所に応じた使い分けが重要になります。
雪見灯籠は、丸みのある大きな笠と低めの背丈が特徴です。池のそばや苔庭に合わせると、落ち着いた和の雰囲気を演出できます。足が3本または4本あるため安定性が高く、庭石の上などにも設置しやすいというメリットがあります。
一方、春日灯籠は高さがあり、神社仏閣を思わせる荘厳な印象を持つ灯籠です。格式ある和風庭園や広めの敷地に適しており、庭の主役として使いたい場合に選ばれます。
置灯籠はコンパクトで扱いやすく、玄関アプローチや狭小スペースにも設置しやすいのが魅力です。特に住宅の庭に取り入れたい人に人気があり、軽量タイプであれば移動も簡単です。
選び方のポイントとしては、庭全体のバランスを意識することが欠かせません。広い庭に小さな灯籠を置くと埋もれてしまいますし、逆に狭いスペースに大型の灯籠を置くと圧迫感が出ます。また、地震のリスクや安全性も考慮し、人通りの多い場所には安定感のあるタイプを選ぶのが理想的です。
照明としての実用性よりも、庭の景観としての効果が重視される傾向にあるため、周囲の植栽や石材との調和も忘れず確認しておきましょう。
灯籠インテリアとしての活用法

灯籠は庭園や墓所に限らず、屋内外のインテリアとしても注目されています。落ち着いた雰囲気や和の趣を演出できるアイテムとして、多くの住宅や商業施設で活用されているのが現状です。
特に人気があるのは、電球やLEDライトを組み込んだ「照明用灯籠」です。玄関やテラスのアクセントとして設置すると、夜間でも柔らかく空間を照らし、訪れる人に安らぎを与える効果があります。
また、屋内に設置するケースも増えています。和室の一角や床の間、さらには飲食店のディスプレイなどに、小型の置灯籠を取り入れることで、空間全体に和のテイストが加わります。あえて明かりを灯さず、オブジェとして飾るだけでも十分な存在感を持たせることができます。
ただし、屋内に使用する場合はサイズと重量に注意が必要です。特に石製のものは重いため、床材を傷つけないように下敷きをするなどの工夫が求められます。湿気の多い場所では、素材によっては劣化が早まる可能性もあるため、設置場所には十分配慮しましょう。
これを活かせば、和モダンや和洋折衷スタイルの空間づくりにも役立ちます。静けさや落ち着き、季節感を取り入れるアイテムとして、灯籠は非常に優秀なインテリア要素と言えるでしょう。
燈篭の役割は何か?仏教的な意味とは
燈篭(とうろう)は、単なる照明器具ではなく、仏教において重要な象徴的意味を持っています。火を灯すことによって、故人を供養し、魂を安らかに導くと信じられてきました。
仏教の供養には「五供(ごくう)」と呼ばれる5つの基本的なお供えがあります。「香」「花」「水」「飲食(おんじき)」「灯燭(とうしょく)」の5つで、そのうちの「灯燭」が燈篭の役割に該当します。灯燭は火によって邪気を払い、仏や故人の魂を清めるとされる神聖な行いです。
例えば、お墓の前に設置された燈篭にろうそくの火を灯す行為は、亡くなった方への供養であると同時に、参拝する者自身の心を整える意味も含まれています。また、火が道しるべとなることで、故人の魂が迷うことなく成仏できるよう導くとも考えられています。
現代では実際に火を灯す場面は少なくなりましたが、多くの燈篭には月や太陽をモチーフにした彫刻が施されています。これは、常に灯がともっていることを象徴し、形そのものに供養の意味が宿っていると考えられています。
このように、燈篭はただの装飾品ではなく、古くから続く精神的な意味合いを含んだ重要な存在です。特に仏教に基づいた供養を重んじる家庭では、灯りの意味を改めて知ったうえで設置を検討することが望ましいでしょう。
購入前に知っておきたい灯籠の置き方と価格帯

庭や墓に置く灯篭の置き方ガイド

灯篭を庭や墓に設置する際には、見た目のバランスだけでなく、正しい置き方を理解しておくことが大切です。誤った設置は、安全性を損なうだけでなく、本来の役割や雰囲気を台無しにする恐れがあります。
まず、火袋(ひぶくろ)の向きに注意が必要です。一般的に、火袋には丸い穴と三日月形の穴があり、丸い穴を東向き、三日月を西向きに配置するのが伝統的な設置方法とされています。これは、太陽と月を象徴する向きであり、灯りが一日中絶えず灯っているという意味を持たせるためです。
庭に設置する場合は、人の通り道や植物との距離を考え、圧迫感を与えない配置にすることが重要です。特に雪見灯篭のように足の広がったデザインは、安定感がある一方で設置スペースが必要になります。通路や玄関に近い場所には、小型の置灯籠が扱いやすく適しています。
墓前に設置する灯篭は、通常一対で左右に配置します。ただし、スペースの都合で一基のみ置く場合は、墓石から見て右側(参拝者から見ると左側)に設置するのが一般的です。これは「右尊左卑(うそんさひ)」という古来の考え方に基づいています。
設置時は、必ず水平な地面を選び、基礎がしっかりした場所に設置しましょう。地震などの影響で倒れやすくなることを避けるため、必要に応じて固定用のプレートや接着剤を使用することもあります。
また、重たい石灯篭を自力で動かすのは危険です。特に大きめの灯篭は、専門の施工業者に相談するほうが安全で安心です。
燈篭と灯籠の違いを知っておこう
「燈篭」と「灯籠」は、どちらも「とうろう」と読みますが、使用される場面や意味には微妙な違いがあります。見た目には似ているこの2つの表記ですが、文字に込められた意味を知っておくと、より深い理解につながります。
まず、「灯籠」は現在もっとも一般的に使われている表記です。石、金属、木などの素材で作られる照明器具全般を指し、寺院や庭園、神社などで見かける装飾的な灯りが該当します。主に固定式であり、屋外に設置されることが多いのが特徴です。
一方で、「燈篭」はより古典的・伝統的な表記とされ、特に仏教的な儀式や行事で用いられることがあります。燈の字には「神聖な火」や「浄化の光」といった意味合いが込められており、法要や供養の場面ではこちらの表記が好まれる傾向があります。
また、素材や用途の違いにも注目すると良いでしょう。たとえば、「燈篭」という語は紙や布を使った可搬式の照明器具、いわゆる提灯や行灯などの意味合いを含む場合もあります。これに対して「灯籠」は、石灯籠のように据え置き型の構造物を指すことが多いです。
このように、文字の違いには使われる場面や文化的背景が関係しています。どちらも正しい言葉ではありますが、目的や文章の文脈に応じて使い分けることが望ましいと言えるでしょう。
高級石材と安価灯籠の価格差とは?

灯籠の価格を左右する最大の要素の一つが、使用されている石材の種類です。特に国産の高級石材と、海外産の比較的安価な石材では、見た目だけでなく耐久性や質感にも大きな違いがあります。
国産の高級石材として有名なのは、岡崎中目石・蛭川石・万成石などです。これらは日本国内で採掘され、加工も熟練の職人によって行われるため、灯籠1基でも数十万円から、デザインや仕上げによっては100万円以上になることがあります。細部の仕上げが滑らかで、長期間風雨にさらされても劣化しにくい点が評価されています。
一方、安価な灯籠には中国産やインド産などの輸入石材がよく使われています。価格は3万円〜10万円程度と比較的手に入りやすく、特に初めて灯籠を導入する方や、複数基設置したい方にとっては選びやすい選択肢です。ただし、表面の仕上げが粗かったり、経年劣化が早かったりすることもあるため、設置場所や使用目的に合った判断が必要です。
このように、石材のグレードや加工技術によって価格に大きな差が生じます。見た目の違いだけでなく、長期的なメンテナンス性や景観との調和も考えて選ぶようにしましょう。
おすすめの灯籠購入先と選び方
灯籠を購入する際には、購入先によって得られる情報やサービスに違いがあります。主な選択肢としては、石材店とインターネット通販の2つが挙げられます。
石材店では、実物を見ながら選べるというメリットがあります。質感やサイズ感を直接確認できるため、失敗が少なく、担当者に用途や設置場所を相談しながら最適なものを選ぶことができます。特に国産石を扱う専門店では、オーダーメイドにも対応してくれることが多く、こだわりのある方には最適です。
一方、インターネット通販は、手軽に価格やデザインを比較できる点が魅力です。自宅にいながら多数の選択肢を閲覧できるため、忙しい方や近くに石材店がない場合にも便利です。ただし、サイズ感や色味が実物と異なる可能性があるため、レビューや写真をよく確認することが欠かせません。
選び方のポイントとしては、設置場所の広さ、雰囲気との相性、予算、そしてメンテナンス性をバランスよく考慮することが重要です。特に重量がある石灯籠は、配送方法や設置支援の有無も確認しておくと安心です。
購入後に後悔しないためにも、デザインだけでなく、使用目的と現場環境に合った灯籠を選ぶことが成功のカギとなります。
和風庭園に最適な灯籠の選定基準

和風庭園に灯籠を取り入れることで、空間全体の雰囲気が引き締まり、より趣のある庭を演出できます。ただし、どの灯籠でも合うわけではなく、庭の構造やテーマに合わせた選定が重要です。
まず注目したいのは、灯籠の高さと設置位置です。広い庭には背の高い春日灯籠が映えますが、狭い庭や低木の多い場所では、雪見灯籠や置灯籠など低めのデザインが自然に溶け込みます。高低差をつけることで、庭全体に奥行きが生まれる効果も期待できます。
また、素材の質感と色合いも重要な要素です。自然石風の仕上げや、苔が付きやすいムシリ加工などは、時間とともに庭に馴染みやすく、侘び寂びの美を感じさせます。庭の苔や石組み、水辺などとの相性を考えながら選ぶことで、統一感のある景観が完成します。
さらに、設置する場所の安全性にも配慮が必要です。通路付近に設置する場合は、つまずきにくいサイズや形状を選び、地震対策として安定した基礎を用意することをおすすめします。
単に「おしゃれ」に見えるかどうかではなく、空間全体のバランスと、灯籠そのものが持つ文化的背景を理解したうえで選定することで、和風庭園の完成度が格段に高まります。
灯籠の値段の相場から考える選び方と設置のポイント
- 灯籠の値段の相場は3万円〜10万円程度が中心
- 高級な国産石材を使う灯籠は100万円を超える場合もある
- 価格は素材・加工技術・デザインの細かさで決まる
- 中国産などの輸入石材を使った灯籠は比較的安価
- 春日灯籠は背が高く格式ある場所に適している
- 雪見灯籠は池や庭に適した落ち着いたデザイン
- 置灯籠はコンパクトで玄関や狭い庭に向いている
- 活込灯籠は茶庭や坪庭に映える埋め込みタイプ
- インテリアとしてはLED灯籠が人気で使いやすい
- 屋内に置く場合は重量や床材への配慮が必要
- 燈篭は仏教の供養における灯燭の役割を持つ
- 庭や墓には火袋の向きや配置ルールがある
- 灯籠の設置には2万円〜5万円程度の施工費がかかる
- 石材店は実物を見ながら購入できる安心感がある
- 和風庭園には高さや色合いを考慮した灯籠選びが重要
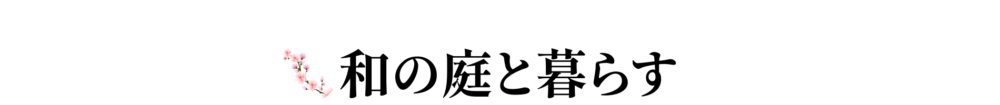



コメント